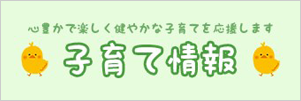ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
本文
文化財について紹介します
国指定文化財
- 三段峡
- 押ケ峠断層帯
県指定文化財
- 吉水園
- 吉水園のモリアオガエル
- 紙本著色隅屋鉄山絵巻
- 下筒賀の社倉
- 湯立神楽
- 太鼓おどり
- 堀八幡の流鏑馬
- 坂原神楽
- 筒賀のイチョウ
- 願福寺薬師堂
- 黒韋威胴丸
- 太刀附鉄はばき
- 梶ノ木の大スギ
- 洗川の谷渡り台杉
町指定文化財
- 川舟関係用具
- 加計げんこつ踊り
- 吉水園の淡水海綿
- 殿賀田楽
- 遅越第一号古墳
- 八幡神社石燈篭
- ※指定解除
- 津浪河内神社のスギの群生
- 辻ノ河原のサイジョウガキ
- 神楽-四神-
- 早木のスイリュウヒバ
- 古寺尾のウラジロガシ
- 堀八幡神社玉殿
- 横山霊岸寺観音堂厨子
- 木造阿弥陀如来像
- 絹本著色親鸞聖人伝絵
- 木造阿弥陀如来立像
- 西光寺山城跡
- 梶原山城跡
- 田之尻の猪垣
- 龍頭峡
- 悠久の森
- 砂ケ瀬の猪垣
- 上殿囃子田
- 実際寺の開山塔
- 円光寺の山門
- 円光寺の弥陀三尊仏
- 平見谷大歳神社の社叢
- 猪山大歳神社の社叢
- 奥ノ原鉱山跡の磁鉄鉱鉱床の露頭
- 宗玄寺の石塁
- 桜尾城跡
- 堀八幡神社の本殿
- 長尾神社本殿
- 正覚寺経蔵
- 実際寺木造雪舟禅師倚像
- 諏訪神社隨身倚像
- 諏訪神社狛犬
登録文化財
- 旧筒賀村役場庁舎
- 株式会社日新林業加計出張所
国指定文化財
| 番号 | 指定 | 種別 | 名称 | 員数 | 構造・形式・大きさ等 | 沿革・その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | (種類) | (指定年月日) | ||||
| 分類 | ||||||
| 1 | 国 | 特別名勝 | 三段峡 | 一帯 | 太田川の支流柴木川沿いに広がる長さ約10kmの峡谷で、無数の滝や大岩壁が数多く見られる | 大正14年10月8日、国名勝の指定を受ける。 |
| 名勝 | (峡谷) | 上流域は山県郡芸北町域 | ||||
| 記念物 | (昭和28年11月14日) | |||||
| 2 | 国 | 天然記念物 | 押ケ峠断層帯 | 一帯 | 太田川上流の立岩ダムから坂根集落に至る2kmの間、左岸に位置する線状に並ぶ四個の断層丘陵(ケルンバット) | 4個の断層丘陵はそれぞれ「タオ,ニゴヤ」などと呼ばれている。 |
| 天然 | (地層) | 断層帯はこれら断層丘陵の西側鞍部(ケルンコル)を結ぶ線に沿って走り、さらに北東及び南西方向に延長20kmに及ぶ地質学・地形学上顕著な断層である。 | ||||
| 安芸西武山地の谷間に見られるこのような典型的断層地形は、我が国では他に類例がなく、学術上価値が高い | ||||||
| 記念物 | (昭和40年7月1日) | |||||
| 計 | 2 | 特別名勝1,天然記念物1 | ||||
県指定文化財
| 番号 | 指定 | 種別 | 名称 | 員数 | 構造・形式・大きさ等 | 沿革・その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | (種類) | (指定年月日) | ||||
| 分類 | ||||||
| 1 | 県 | 名勝 | 吉水園 | 一ケ所 | 入母屋造茅葺吉水亭,金屋子神社,薬師堂,玉壷池等で構成された廻遊式庭園 | 天明元年(1781)、加計16代当主佐々木八右衛門正任が造営。庭師は京都の清水七郎右衛門。 |
| 名勝 | (庭園) | (昭和26年7月10日) | ||||
| 記念物 | ||||||
| 2 | 県 | 天然記念物 | 吉水園のモリアオガエル | 一 | メス7cm,オス4cm前後。 | 池の上に張り出した木の枝でに直径10cm前後の白い泡状の塊をつける。 |
| 天然 | (生物) | (昭和27年10月28日) | 群 | 園内では、集団の産卵風景を観察できる。5月上旬~6月下旬が産卵期 | ||
| 記念物 | ||||||
| 3 | 県 | 重要文化財 | 紙本著色隅屋鉄山絵巻 | 二巻 | 第一巻長さ740cm,幅24cm,第二巻長さ760cm,幅24cm | 鉄山研究の貴重な資料。川・森・文化・交流センター2階歴史民俗資料館前に複製を展示 |
| 美術 | (美術工芸品) | (昭36年4月18日) | 描写は極めて写実的 | |||
| 有形文化財 | ||||||
| 4 | 県 | 史跡 | 下筒賀の社倉 | 一棟 | 切妻造茅葺の土蔵。 | 江戸中期(17世紀後半)に建立されたもの。社倉法により飢饉に備えて穀物を蓄えた。 |
| 史跡 | (建造物) | (昭和36年11月1日) | 建坪は約4坪。県下では数少ない現存の建物として指定 | |||
| 記念物 | ||||||
| 5 | 県 | 無形民俗文化財 | 湯立神楽 | - | 樂奏者4人とともに、素面の舞人3人が幣と鈴または剣と鈴を手に舞う | 江戸中期から伝わるこの湯立神楽は、祭祀の前に神事を行い、続いて湯立の舞を奉納する |
| 無形民俗 | (その他) | (昭和38年11月4日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 6 | 県 | 無形民俗文化財 | 太鼓おどり | - | 締太鼓,鉦,横笛の囃子により花笠と浴衣姿で踊る。 | 虫送り行事が原型といわれ、1591年に出雲地方から伝授されたと江戸時代後期の記録有 |
| 無形民俗 | (その他) | (昭和43年1月12日) | 全国的にも優れた歌詞が残る | |||
| 民俗文化財 | ||||||
| 7 | 県 | 無形民俗文化財 | 堀八幡の流鏑馬 | - | 古式に則り長さ140mの馬場の3か所に立てられた的を馬上から次々に鏑矢で騎射する | 戦国時代からの伝承といわれ、境内の資料館には、古い馬具,草木染め衣装,弓などが展示 |
| 無形民俗 | (その他) | (平成9年5月19日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 8 | 県 | 無形民俗文化財 | 坂原神楽 | ― | 旧舞の14曲を大体昔の型のままで伝承。 | 旧舞の南限の地となっている点を評価。衣装も昔のままの布を用いている点も貴重 |
| 無形民俗 | (その他) | (昭和61年11月25日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 9 | 県 | 天然記念物 | 筒賀のイチョウ | 一 | 樹高約48m, | 樹勢は旺盛で、本殿前をおおうばかりの見事な樹冠を形成 |
| 天然 | (樹木) | (昭和24年8月12日) | 株 | 目通り幹囲9.85m | ||
| 記念物 | 県内有数の巨樹 | |||||
| 10 | 県 | 重要文化財 | 願福寺薬師堂 | 一棟 | 方三間,宝形造,桟瓦葺,向拝付 | 江戸時代初期,17世紀後半頃の建立。辻堂的な小堂。屋根は当初は茅葺と推測される |
| 建造物 | (建造物) | (平成3年12月12日) | 堂内に安置されている薬師如来像や十二神将は1551年作 | |||
| 有形文化財 | ||||||
| 11 | 県 | 重要文化財 | 黒韋威胴丸 | 一領 | 高さ65cm,当地の豪族栗栖氏寄進と伝える。南北朝時代の作と推定される | 現存する同様式の胴丸は、全国的にみて遺品が少なく貴重 |
| 美術 | (美術工芸品) | (昭和58年11月7日) | ||||
| 有形文化財 | ||||||
| 12 |
県 |
重要文化財 | 太刀附鉄はばき | -口 | 刃長86.7cm,反り2.8cm | 豪壮な姿の作刀が多く造られた南北朝時代の特徴をよく示している |
| 美術 | (美術工芸品) | (平成5年2月25日) | 大振りに作られ、身巾が広く総体的に長寸で、切先は長い | |||
| 有形文化財 | ||||||
| 13 | 県 | き念物 | 梶ノ木の大スギ | 一株 | 樹高36m,胸高幹囲10.13mの県内有数の大スギ | 平成3年の19号台風による強風により主幹部分が倒木した |
| 天然 | (樹木) | (昭和59年1月23日) | 推定樹齢800年以上 | |||
| 記念物 | ||||||
| 14 | 県 | 天然記念物 | 洗川の谷渡り台杉 | - | 谷を横切る「杉並び」は大小12本からなる。両端の2本ずつはそれぞれ互いに地下部でつながっている | 倒れた杉が谷に向こう側に達し、その梢から発生した枝が地中に根を下ろし成木となっている大変珍しい例 |
| 天然 | (樹木) | (昭和62年12月21日) | ||||
| 記念物 | ||||||
| 計 | 14 | 有形文化財美術3、有形文化財建造物1、無形文化財0,無形民俗文化財4,有形民俗文化財0,史跡1,名勝1,天然記念物4 | ||||
町指定文化財
| 番号 | 指定 | 種別 | 名称 | 員数 | 構造・形式・大きさ等 | 沿革・その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | (種類) | (指定年月日) | ||||
| 分類 | ||||||
| 1 | 町 | 有形民俗文化財 | 川舟関係用具 | 一式 | 川舟の櫓,櫂,網や船頭が身に付ける衣類や携行物 | 川・森・文化・交流センター玄関ロビー及び同2階の歴史民俗資料館に展示。 |
| 有形民俗 | (その他) | (昭和37年7月1日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 2 | 町 | 無形民俗文化財 | 加計げんこつ踊り | - | 揃いの浴衣に編笠、背中に行灯を背負い、左手に筒型の提灯、右手に鳴子を持つ。蝋燭が灯る | 元来は鳥追いの鳴子を用いて踊る豊年踊りの一種。丁川地区のみに伝わる。 |
| 無形民俗 | (その他) | (昭和38年1月12日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 3 | 町 | 天然記念物 | 吉水園の淡水海綿 | 一群 | 無色透明で最も原始的な多細胞動物。 | 吉水園内の「玉壷池」に棲息。 |
| 天然 | (生物) | (昭和42年6月10日) | 『ヌマカイメン』と思われる | |||
| 記念物 | ||||||
| 4 | 町 | 無形民俗文化財 | 殿賀田楽 | - | 六調子,八調子,中の調子の3調子で舞われる。簓,大太鼓,小太鼓,調子鉦,早乙女で構成 | 殿賀地方に伝わる田植囃子。 |
| 無形民俗 | (その他) | (昭和56年11月30日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 5 | 町 | 史跡 | 遅越第一号古墳 | 一ケ所 | 円墳,横穴式石室 | |
| 史跡 | (古墳) | (昭和59年4月1日) | 面積=953平方メートル(未発掘地域含む) | |||
| 記念物 | ||||||
| 6 | 町 | 重要文化財 | 八幡神社石燈篭 | 一 | 高さ5.5m,笠部分は8畳敷(13.2平方メートル)の広さで、亀の形。 | 安政4年(1857)建立。笠石は対岸の高下から運ばれ、その際神の使いの亀に助けられた逸話 |
| 建造物 | (石造物) | (昭和60年1月10日) | 石 | 自然石では日本一といわれる。 | ||
| 有形文化財 | ||||||
| 8 | 町 | 天然記念物 | 津浪河内神社のスギの群生 | 八株 | (8本中最大木の数値) | 神社の社殿を取り囲むように巨樹8本がそびえている。神社は永和元年(1375)建立。 |
| 天然 | (樹木) | (平成9年1月23日) | 胸高幹囲4.85m,樹高40m, | |||
| 記念物 | 推定樹齢600年 | |||||
| 9 | 町 | 天然記念物 | 辻ノ河原のサイジョウガキ | 一 | 胸高幹囲3.32m,樹高16m | 伝承によると「飢餓の時に干し柿にしておく役があった。」といわれ、歴史的意義を持つ。 |
| 天然 | (樹木) | (平成9年1月23日) | 株 | 推定樹齢500年 | ||
| 記念物 | 県内第1位(県文化財協会資料) | |||||
| 10 | 町 | 無形民俗文化財 | 神楽-四神- | 4人の舞子が烏帽子をかぶり、垂直に袴をはき、小さな柄のない幣と鈴,後に扇子と鈴で舞う | 儀式舞。石見神楽矢上系の流れをくむ芸北町橋山神楽団より伝授される。 | |
| 無形民俗 | (その他) | (平成10年1月23日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 11 | 町 | 天然記念物 | 早木のスイリュウヒバ | 一 | 胸高幹囲2.87m,樹高12m | 一般には「スイリュウ」といわれる。樹高,幹囲の大きさにおいて、この種として貴重。 |
| 天然 | (樹木) | (平成11年5月28日) | 株 | 推定樹齢280~300年 | ||
| 記念物 | ||||||
| 12 | 町 | 天然記念物 | 古寺尾のウラジロガシ | 一 | 胸高幹囲7.35m,樹高22m | 幹根元部分は火災により空洞化。しかし、樹勢が急激に損なわれるとは考えられない。 |
| 天然 | (樹木) | (平成14年7月5日) | 株 | 推定樹齢800年 | ||
| 記念物 | 胸高幹囲県内第1位,樹高2位 | |||||
| 13 | 町 | 重要文化財 | 堀八幡神社玉殿 | 一 | 三間社,流造,柿葺 | 15世紀中期~後期の建立。室町時代前期~中期の建築様式を残す貴重な建築史料。 |
| 建造物 | (建造物) | (平成16年3月17日) | 基 | 幅48.5寸,奥行25.2寸,高さ38.8寸 | ||
| 有形文化財 | ||||||
| 14 | 町 | 重要文化財 | 横山霊岸寺観音堂厨子 | 一 | 土居桁,円柱,木鼻付き,如意頭屋根,正面桟唐戸。幅20寸,奥行14.2寸,高さ35.8寸 | 1522年建立(墨書銘)。細部の造りも本格的な唐様の本格的な厨子。 |
| 建造物 | (建造物) | (平成16年3月17日) | 基 | |||
| 有形文化財 | ||||||
| 15 | 町 | 重要文化財 | 木造阿弥陀如来像 | 一躯 | 寄木造,安阿弥風の仏像, | 室町時代の作と推定 |
| 美術 | (美術工芸品) | (平成6年6月23日) | 台座は八菱形三段框, | |||
| 有形文化財 | 像高39cm,台座高22.5cm | |||||
| 16 | 町 | 重要文化財 | 絹本著色親鸞聖人伝絵 | 四幅一対 | 色彩が鮮やかで筆致が精巧,図柄が古風。 | 江戸時代17世紀後半の作。収納箱に宝永元年(1704)とある |
| 美術 | (美術工芸品) | (平成6年6月23日) | 一幅が横80cm,縦190cm | |||
| 有形文化財 | ||||||
| 17 | 町 | 重要文化財 | 木造阿弥陀如来立像 | 一躯 | 寄木造,安阿弥風の仏像,台座は八菱形三段框,像高39cm,台座高22.5cm | 室町時代末期の作と推定される。明治44年本山東坊住職より譲り受けたもの |
| 美術 | (美術工芸品) | (平成6年6月23日) | ||||
| 有形文化財 | ||||||
| 18 | 町 | 史跡 | 西光寺山城跡 | 一ケ所 | 立地は丘陵先端,4郭を中心とする小規模な郭群 | 室町時代中期 |
| 史跡 | (山城跡) | (平成6年6月23日) | 頂部の一郭は25m×20m | 栗栖氏一族の居城 | ||
| 記念物 | ||||||
| 19 | 町 | 史跡 | 梶原山城跡 | 一ケ所 | 遺構は最高所に構えた一郭を中心に、三方に分かれ尾根を加工した郭群と堀切からなる | 室町時代中期 |
| 史跡 | (山城跡) | (平成6年6月23日) | 栗栖河内の居城(芸藩通誌) | |||
| 記念物 | ||||||
| 20 | 町 | 史跡 | 田之尻の猪垣 | 一ケ所 | 石塁が7アールぐらいの畑(現在は山林)を囲む形で斜面に沿って築工。全長81.5m,石塁の高さ2m前後 | 原形がよく残っている。造られたのは元禄期か享保年間と推定される |
| 史跡 | (構造物) | (平成6年6月23日) | ||||
| 記念物 | ||||||
| 21 | 町 | 名勝 | 龍頭峡 | 一ケ所 | 高さ126mの岸壁からなる「追森の滝」落差40mの「二段滝」落差20mの「奥の滝」約2kmの龍頭渓谷からなる | 寛政9年都志見往来日記に紹介され「芸藩通誌」にも絵と文が記述されている |
| 名勝 | (峡谷) | (平成6年6月23日) | ||||
| 記念物 | ||||||
| 22 | 町 | 名勝 | 悠久の森 | 一ケ所 | 原生的天然林「引明の森」究極の人工林「横泓の森」と「分収育林」からなっている | 平成2年(1990)7 |
| 名勝 | (自然林) | (平成6年6月23日) | 月「悠久の森条例」を定めた。村有林100周年の歴史が基盤 | |||
| 記念物 | ||||||
| 23 | 町 | 史跡 | 砂ケ瀬の猪垣 | 一ケ所 | 全長300mの石塁。イノシシやシカからの「シシ除け」の構造だけでなく、捕獲や落石防止の役割も考えられる | 享保20年(1735)ごろの築造と推定される。(古文書等にはっきりした記録はない。) |
| 史跡 | (構造物) | (平成7年9月6日) | ||||
| 記念物 | ||||||
| 24 | 町 | 無形民俗文化財 | 上殿囃子田 | 現在,16種類の手合わせに,中ばやし,苗取り,さんばいの神迎え,神送りまで構成して演技することができる | 古くからの伝統そのままの揺歌が伝承されていることは大変貴重 | |
| 無形民俗 | (その他) | (平成元年3月10日) | ||||
| 民俗文化財 | ||||||
| 25 | 町 | 重要文化財 | 実際寺の開山塔 | 一 | 高さ106cm,幅最大50cm最小32cm | 雪舟禅師がなくなった永和元(1375)年後の14世紀末ごろ造立と推察される |
| 建造物 | (建造物) | (平成4年1月27日) | 基 | 花崗岩製の無縫搭 | ||
| 開山した雪舟嘉猷禅師の墓搭 | ||||||
| 有形文化財 | ||||||
| 26 | 町 | 重要文化財 | 円光寺の山門 | 一 | 高さ430cm,幅244cm,奥行192cm | 元文2(1737)年の建立。両袖門がつき,懸魚,蟇股など細部には鎌倉時代の手法が |
| 建造物 | (建造物) | (平成4年1月27日) | 基 | 木造四脚門(棟札が残る) | ||
| 有形文化財 | ||||||
| 27 | 町 | 重要文化財 | 円光寺の弥陀三尊仏 | 三躯 | 阿弥陀如来立像80.5cm | 各部の特徴から室町時代中期の作品といわれ、この地方で三尊形式である点は珍しい |
| 美術 | (美術工芸品) | (平成4年1月27日) | 聖観音菩薩立像53.0cm | |||
| 勢至観音菩薩立像 54.0cm | ||||||
| 有形文化財 | (いずれも寄木造り) | |||||
| 28 | 町 | 天然記念物 | 平見谷大歳神社の社叢 | 一ケ所 | スギ46本ヒノキ3本アカマツ2本 | 胸高5.24m、高さ34mのスギは県内でも有数の巨木 |
| 天然 | (樹木) | (平成7年7月6日) | ナラ1本シデ1本 | |||
| 記念物 | ||||||
| 29 | 町 | 天然記念物 | 猪山大歳神社の社叢 | 一ケ所 | スギ31本,モミ50本,ナラ2本,クリ2本,イロハカエデ2本,ホウノキ3本,ヒノキ2本,ソヨゴ1本,イタヤカエデ2本,アベマキ1本 | スギ,モミを中心とする巨樹群。境内の建物近くに巨樹が密生するという珍しい景観を示している |
| 天然 | (樹木) | (平成7年7月6日) | ||||
| 30 | 町 | 天然記念物 | 奥ノ原鉱山跡の磁鉄鉱鉱床の露頭 | 一ヶ所 | 奥ノ原山山頂付近の標高1020.6mの稜線沿いにある。稜線を6mあまり掘り下げられており、その付近から西斜面にかけて、南北方向に露天堀りの跡と磁鉄鉱鉱床の露頭が見られる。 | 二畳紀(約2億5千万年前)の地層に白亜紀末期(約7千万年前)に花こう岩が貫入して出来たスカルン鉱床であり、露天堀りの跡と磁鉄鉱鉱床の露頭が見られる。 |
| 天然 | (記念物) | (平成17年10月28日) | 0.074ヘクタール | |||
| 31 | 町 | 史跡 | 宗玄寺の石塁 | 一ヶ所 | この石塁は、その構造から中世に築造されたものと考えられる。大きな自然石によっており、その広い面を見せる等の築き方は特徴的であって、福井市の一乗谷遺跡に戦国時代の類例が存在しているが、山県郡西部地方ででは他に見当たらない貴重な遺跡である。 | 築いたのは中世、安芸太田地方の開発領主であったという栗栖氏の可能性を指摘できる。栗栖氏は、一族が近接する箕角城(跡)に拠ったと伝えており、その館跡(土居)に近世になって宗玄寺が他から移築されたものと推定される。 |
| 史跡 | (記念物) | (平成17年10月28日) | 経蔵側から北へ30m | |||
| 32 | 町 | 史跡 | 桜尾城跡 | 一ヶ所 | 土居裏山にある標高378mの山頂部に位置する。10以上の郭(曲輪)群と土塁・堀切など、城を構成する各遺構の保存状態は良好。標高320m以上を基本に指定範囲。 | 郭(曲輪)の規模・配置などの特徴から16世紀後半の戦国時代に築城されたものと考えられる。詳細は不明であるが江戸時代の資料によると太田栗栖氏の一族が居城したと推定される。 |
| 史跡 | (記念物) | (平成18年8月10日) | ||||
| 33 | 町 | 重要文化財 | 堀八幡神社の本殿 | 一基 | 三間社流造、銅板葺 | 本殿は、約300年前の江戸時代中期に再建され、現存している貴重な建造物である。平安時代以来の正統の造りが受け継がれるとともに、蓑束など中世の部材を遺し類い稀な価値を持つといえる。 |
| 建造物 | (建造物) | (平成22年3月18日) | ||||
| 有形文化財 | ||||||
| 34 | 町 | 重要文化財 | 長尾神社本殿 | 一基 | 三間社春日造(入母屋造妻入) | 本殿は、約280年前の江戸中期に再建され、和歌山の熊野権現と同じ春日造りで、県内随一という珍しいもの。内陣・内々陣のみで外陣がないのは、早い年代に拝殿から拝んでおり、厳島神社など大社に見られる格式の高い本殿である。 |
| 建造物 | (建造物) | (平成22年3月18日) | ||||
| 有形文化財 | ||||||
| 35 | 町 | 重要文化財 | 正覚寺経蔵 | 一 | 正面三間、柱真々12尺1寸、側面四間、柱真々12尺1寸、宝形造、桟瓦葺、向拝一間、桟瓦葺 | 元禄15(1702)年の建築で広島県内では現 |
| 建造物 | (建造物) | (平成25年3月19日) | 棟 | 附傅太子像1軀 | 存最古の土蔵造の経蔵であり、全国的にみても極めて古く貴重。 | |
| 有形文化財 | 脇侍像 2軀 | |||||
| 一切経 | ||||||
| 36 | 町 | 重要文化財 | 実際寺 | 一 | 像高 34.0cm | 篤実そうな表情や袖の写実的な表現の仕方など、小型ながら雪舟禅師の遺徳を偲ぶことのできる貴重な彫刻。本体や曲ろくの一部に破損が見られるが、保存状態は良好。 |
| 美術 | (美術工芸品) | 木造雪舟禅師倚像 | 躯 | |||
| 有形文化財 | (平成25年3月19日) | |||||
| 37 | 町 | 重要文化財 | 諏訪神社隨身倚像 | 一対 | 隨身像は二体から成るが、両像とも木造で袖端を別に作る寄木造。冠束帯の彫り方は、表現が乏しいが、地方の作らしい荒々しさを感じることができ、安芸太田町の文化を知る上で貴重。 | |
| 美術 | (美術工芸品) | (平成25年3月19日) | ||||
| 有形文化財 | 木造(寄木造) | |||||
| 左隨身倚像 47.0cm | ||||||
| 右隨身倚像 47.5cm | ||||||
| 38 | 町 | 重要文化財 | 諏訪神社狛犬 | 一対 | 阿形狛犬高さ 32.5cm | 諏訪神社の狛犬は、阿形と吽形の一対であり全体の形状から十六世紀前期に制作されたものと考えられる。保存状態は概ね良好。 |
| 美術 | (美術工芸品) | (平成25年3月19日) | 長さ 22.5cm | |||
| 有形文化財 | 吽形狛犬高さ 31.5cm | |||||
| 長さ 18.5cm | ||||||
| 計 | 37 | 有形文化財美術7、有形文化財建造物8、無形文化財0,無形民俗文化財4,有形民俗文化財1,名勝2,史跡7,天然記念物8 | ||||
国登録文化財
| 番号 | 指定 | 種別 | 名称 | 員数 | 構造・形式・大きさ等 | 沿革・その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | (種類) | (指定年月日) | ||||
| 分類 | ||||||
| 1 | 国 | 登録文化財 | 旧筒賀村役場庁舎 | 一棟 | 当庁舎は、昭和11年4月27日に落成し、筒賀村有林の木材を使った宝形造の2階建の建物である。角型花崗岩の切石で化粧をしたコンクリートの布基礎をめぐらし、外壁はモルタル塗、腰壁はスクラッチタイル張りで半円アーチ型の玄関ポーチとともに、2階中央部分には華やかな装飾を設けるなど意匠的に大きなアクセントになっている。 | |
| 登録 | (建造物) | (平成22年5月20日) | ||||
| 木造2階建瓦葺 | ||||||
| 有形文化財 | 建築面積247平方メートル | |||||
| 2 | 国 | 登録文化財 | 一棟 | 大正10年に建てられ形式は土蔵造町屋で、鉄格子付むしこ窓、室内は銀行らしく高い天井で、重層部の窓が天窓の役割をなしている。 | ||
| 登録 | (建造物) | 昭和41年に改修されたが、山間村落の近代化を示す建造物として高く評価されている。 | ||||
| 株式会社日新林業加計出張所 | ||||||
| 有形文化財 | (旧加計銀行、旧広島銀行加計支店) | 木造平屋建、瓦葺、建築面積61平方メートル | ||||
| 計 | 2 | 有形文化財建造物2 | ||||